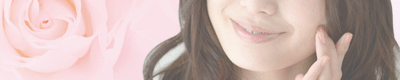ネクタイを理解するための10冊













 がなくて、、、
がなくて、、、 と
と ですることに。
ですることに。

テーマは、




��で、




こちらも




とにかく





唯一の一枚





ネクタイあしたのもと
《やっと秋が来て、涼しい、いい季節になったね》
と書きたいんだけど、いつまでも暑くて、ちっとも夏が終わらない。
沈黙図書館を一週間休館して、アクセスの動向を調べていたんだけど、新しくブログを更新していないのに、かなりの数の人が繰り返して、《過去ブログ》を読んでくれている。とくに、ヒデキものはフォロワーが多い。やはり芸能ネタにアクセスが多いのだが、自分話もけっこう読んでくれている。
前回の《J-f#903》では、詳しい説明をしなかったが、三月の初めからずっと毎日新しいブログを半年以上にわたって書きつづけてきて、自分でも、オレは本当は飽きっぽい性格なのによく半年もつづいたなあというのが正直な感想なのだが、どんなに面白い、刺激的なことでも半年間にわたって毎日、というと、やはりルーチン・ワークになっていく。
ネタはいくらでもあり、忘れられない人も忘れられない事件も、是非書いておきたいこともまだまだあるのだが、自分のなかにちゃんと説明できない[疲弊]があり、ブログの執筆を不定期にすることにしたのである。すべては、《マンネリズムとどう戦うか》という新しいクリエイティブを求める精神的欲求なのだ。
それで、また、しばらくチチ、珍○コじゃなかった、[珍黙図書館]を開館する。
今日から四日間連続して沖縄のことを書こうと思う。政治的なことも含めてである。
まず『週刊読書人』から書評の原稿依頼があった件。前にもこの話はちょっと書いた。その原稿が、先週発売の9月7日号の『〜読書人』に掲載された。
この号の一面は東大教授の哲学者、熊野純彦氏のインタビュー。オレの書いた記事はずっと後ろのページに載っている。
オレの場合、河出書房新社とだけ仲良しで、出版界でも完全に孤立していて、いつも好きなことばかりやっているので、原稿依頼などほとんど来ない。扱いにくいと思われているのだろうが、実際に、若い編集者たちにとっては、オレのように七〇歳過ぎても、原稿書きのエネルギーが落ちていかない編集者・作家は扱いにくいのではないかと思う。それで、『〜読書人』からの書評の注文はカメラマンの長濱治の沖縄の人間たちを取り上げた写真集だった。これが書影。
『創造する魂〜沖縄ギラギラ琉球キラキラ100+2〜』、長濱治著 ワイズ出版刊
定価3700円。
長濱治というのは、こういう人。
古い仕事仲間で、『平凡パンチ』のヌード写真から、『ターザン』、『ガリバー』と付き合ってもらったカメラマン。石川次郎の現場時代の撮影担当だった人のひとり、オレとのつき合いも35年になる。去年は、前田日明の本の装丁の写真を撮影してもらっている。オレたちは彼のことをチョーさんと呼んでいる。写真集のなかには、沖縄の現実のなかでさまざまに生きようとする、人間たちが100人あまり登場する。
例えば、漁師さん。
蛇皮線弾きのミュージシャン。
民宿のおばさん。
この写真集は我々が信仰する[民衆こそが歴史の主役だ]という秘かな思想を体現したものだった。
この写真集について、オレはこういう書評原稿を書いた。
この写真集にはざっと数えてだが、男が七十二人、女が三十四人、子供が五人登場する。ネクタイしている人は二人しかいない。長濱治が生涯をかけて追いつづけた沖縄の文化風土というテーマの、背後に沖縄、あるいは琉球の地霊が写りこんでいるような人間写真ばかりが並んでいる。どの写真からも沖縄の情念と痛ましさと強烈な土俗のエネルギーがあふれ出てくるような気がしながらこの写真集を見せてもらった。
わたしはここで十年ほど前に彼から個人的に聞いた、彼がこの本のなかで説明していない、沖縄にこだわる個人的な事情を本人になんの断りもなく書き添えておこう。なぜ沖縄を撮りつづけてきたのか。彼はこういった。
「オレは十六歳まで名古屋で育ったんだよ。子どものころ、名古屋の疎開先なんだけど、小牧の米軍基地のそばにいたことがあるんだよ。ものごころつくころから、米軍のジープとか軍隊の制服とかブーツとか、カッコいいなと思いながら、いろんなものを見ていた。それこそギブミーチョコレートの世界ですよ。近所にいい女のオネーチャンがいて、それが兵隊のオンリーでね、くさるほどチョコレートをもらって帰ってくる。オレたちはその後をついて回ってギブミーチョコレートってやっていたのよ。ちょっと大きくなってから鉱石ラジオで進駐軍放送聞いて、デューク・エリントンとかグレン・ミラーとか、音楽がかっこよくてビックリした。そのせいでアメリカが大好きだった」
彼の最初の写真集は一九七二年に発表した『暑く長い夜の島』だ。そのころの沖縄で撮った写真をまとめたものだが、これはいま、古本屋で二十万円の値段がついて売っている。長濱が沖縄に行き始めるのは、六〇年代の後半からで返還前でまだ占領下である。
そのころの沖縄には彼が少年時代に経験した《アメリカ》がそのまま残っていたという。そして、彼の沖縄にはもうひとつ、まったく別の大きなこだわりがあった。写真集の途中に、終戦時の沖縄県知事・島田叡(ルビ・あきら)の戦没慰霊塔の写真が唐突な感じで載っている。
「女房と結婚して、オレが沖縄に写真を撮りにいってくるといったら、わたしの伯父さんは島田叡といって、太平洋戦争があった時の最後の県知事だったというんだよ。調べてみたら、大変な人でね。東大を卒業して官僚になった人だった。戦争末期に米軍が攻めてきたらコテンパンにやられると分
かっていて沖縄県知事を引き受けて、『誰かがどうしても行かなきゃならないのならオレがいく。人に死んでくれとはいえない』といって、沖縄に赴任して、知事不在で進まなかった県民の疎開や食糧の確保の問題に取り組んで、最後は米軍の上陸戦に抵抗して戦い、負傷して自決したっていうんだ。その話を聞いたとき、オレは使命みたいなものを感じたんだよ。オレにできることというのは写真を撮ることだけだからね。どうなるか分からないけど、《沖縄》を撮りつづけようと思ったんだよ」
最初に沖縄に行ってみようと思ったきっかけは沖縄出身の大学時代からの友人に招かれてだった。
その人物が真喜志勉、真喜志は一九四一年生まれ、六十四年に多摩美大学洋画科を卒業している、長濱と同年齢、同窓である。二〇一五年に物故しているが、この写真集はたぶん長濱と彼との〝男の約束〟によって作られたものである。
長濱治は多岐にわたる分野で写真を撮りつづけてきた人だが、たぶん、この写真集が、彼のフォトグラファーとしての人生の最終答案なのではないか、そんな気がした。 塩澤幸登(編集者・作家)
この原稿で、たぶん1400字くらいあると思う。ふだん格別に字数制限のない原稿ばかり書いているから、原稿用紙換算で三枚半という文字量は少ないといえば少ないのだが、新聞記事の原稿依頼なのだから、窮屈だがやむを得ないことである。思いのなかのエキスしか書けない。それで、ここから、4回ほどの連載で、オレと長濱の沖縄、オレの沖縄、現実のなかの翁長さんが無念の思いを抱いて死んでいった沖縄の現状についても、書いておこうと思う。
オレは自分のペンが現実を動かすなどとは少しも思っていないが、現実は、特に政治的な状況というのは、それぞれの人たちが思いを共有するところからしか始まらない。それは蟷螂の斧のようなものだが、集まれば[民衆の怒り]になり、バスチーユの牢獄の鉄の扉でさえも破壊されることがあるのだ。
書評中でふれている[島田叡(アキラ)慰霊碑]はこういうもの。義理の伯父さん。
文化としてのアメリカが彼のそもそもの興味の出発点。
沖縄はアジアのなかでのアメリカという国家と文化の指先である。
こういう写真はそれを撮り、本に載せるだけで政治的抵抗であり得る。
オレは言うこととやることの調和が取れている人間が好きなのだが、チョーさんはいい加減に見えて、キチンとしたところがあり、ヤサグレみたいなのにまともなのである。考えて見ると、韓国に連れて行ったり、三宅島の火山の溶岩流のなかで女の裸を撮らせたり、沖縄へも何度も撮影旅行に出かけた。五月みどりのヌードや小柳ルミ子のセミ・ヌードもこの人に撮ってもらった。この人と知り合ったのも、オレが編集者としてけっこういい仕事ができた(自画自賛してもしょうがないことだが)原因のひとつだと思う。
オレたちはとにかく、いい女に弱く日常生活的にはいい加減で不良だったが、仕事の上ではまともで真摯なクリエイターだったと思う。
チョーさんにもいつまでも元気で、いい仕事をしつづけて欲しいと思う。
今日はここまで。明日の[沖縄レポート②琉球の幻を求めて]編に続く。
ネクタイのすべてがここにある。楽天市場は宝の山
いや、ちゃんと見たよ。
って、ふんちゃんを指さしながら
↑ふんちゃんに笑われる始末(^ν^)
箸置きは大量に家にあるのに

ネクタイ 関連ツイート
黒スーツは長船の特徴でしたね…本科山姥切…長船派でしたね… https://t.co/gyMgibJ…
黒スーツは長船の特徴でしたね…本科山姥切…長船派でしたね… https://t.co/gyMgibJ…
黒スーツは長船の特徴でしたね…本科山姥切…長船派でしたね… https://t.co/gyMgibJ…
黒スーツは長船の特徴でしたね…本科山姥切…長船派でしたね… https://t.co/gyMgibJ…